時間の長さを求める計算は、毎日の生活でよく使う大切な計算です。この学習では、始まりの時こくから終わりの時こくまでの時間を求める基本的な方法を学びます。
学習のポイント
- 時間をまたぐときの計算方法を理解する
- 何分間かを正しく求める
- 何時間何分かを求める練習
- 午前から午後にまたがる時間の計算
こちらのプリントもご利用ください
問題例
時こくから時こくまでの時間を求める計算が出来るように練習します。
計算方法はいろいろあります。**ここで紹介している方法は一例です。お子さんが理解しやすい方法で計算できれば大丈夫です。自分なりの解き方を見つけることも大切な学習です。
1. 何分間かを求める
時間をまたぐ場合は、まず「ちょうどの時刻」まで何分あるか考え、そこから終わりの時刻までの分を足します。
例:午後2時40分から午後3時20分まで
- 2時40分から3時まで → 60 − 40 = 20(分)
- 3時から3時20分まで → 20(分)
- 合わせて → 20 + 20 = 40(分)
例:午前7時35分から午前8時10分まで
- 7時35分から8時まで → 60 − 35 = 25(分)
- 8時から8時10分まで → 10(分)
- 合わせて → 25 + 10 = 35(分)
2. 何時間何分かを求める(午前または午後の中で)
時間と分を分けて考えます。
例:午後2時20分から午後5時45分まで
- まず同じ分(20分)まで計算 → 2時20分から5時20分まで → 5 − 2 = 3時間
- 残りの分を計算 → 45 − 20 = 25(分)
- 答え:3時間25分
例:午前8時50分から午前11時30分まで
- まず同じ分(50分)まで計算 → 8時50分から10時50分まで → 10 − 8 = 2時間
- 残りの分を計算 → 10時50分から11時まで → 60 − 50 = 10(分)
- 11時から11時30分まで → 30(分)
- 分を合わせて → 10 + 30 = 40(分)
- 答え:2時間40分
3. 午前から午後にまたがる場合
午後の時刻を24時間制(13時、14時…)にして計算すると分かりやすくなります。
例:午前10時25分から午後1時30分まで
- 午後1時 = 13時として計算
- まず同じ分まで → 10時25分から13時25分まで → 13 − 10 = 3時間
- 分を計算 → 30 − 25 = 5(分)
- 答え:3時間5分
例:午前11時10分から午後4時30分まで
- 午後4時 = 16時として計算
- まず同じ分まで → 11時10分から16時10分まで → 16 − 11 = 5時間
- 分を計算 → 30 − 10 = 20(分)
- 答え:5時間20分
保護者の方へ
お子さんが時間の計算を学ぶ際は、以下の点に注意してサポートしてください:
- 日常生活での活用:学校の時間や習い事の時間など、実生活での例を用いて練習することで理解が深まります。
- 視覚的な補助:時計の模型や図を使って説明すると、より分かりやすくなります。
- 段階的な学習:まず何分間の計算から始め、徐々に何時間何分を含む計算へ進みましょう。
- 繰り返しの練習:定期的に復習し、様々なパターンの問題に取り組むことが大切です。
- 褒めて励ます:小さな進歩も認め、前向きな姿勢を育てましょう。
お子さんの理解度に合わせて、ゆっくりと丁寧に進めていくことが重要です。分からないところがあれば、一緒に考えて解決していきましょう。
時こく時間の学習におすすめ
にがてをとくいにかえる 時こくと単位 小1~6 (算数分野別シリーズ6) 新品価格 | 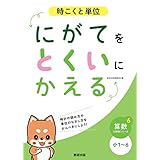 |
練習問題をダウンロードする
画像をクリックするとPDFファイルをダウンロードできます
何分かをもとめる
時計を見て考えてから、計算問題になります
何時間何分をもとめる
時計を見て考えてから、計算問題になります
時間をもとめる
練習問題です。



















